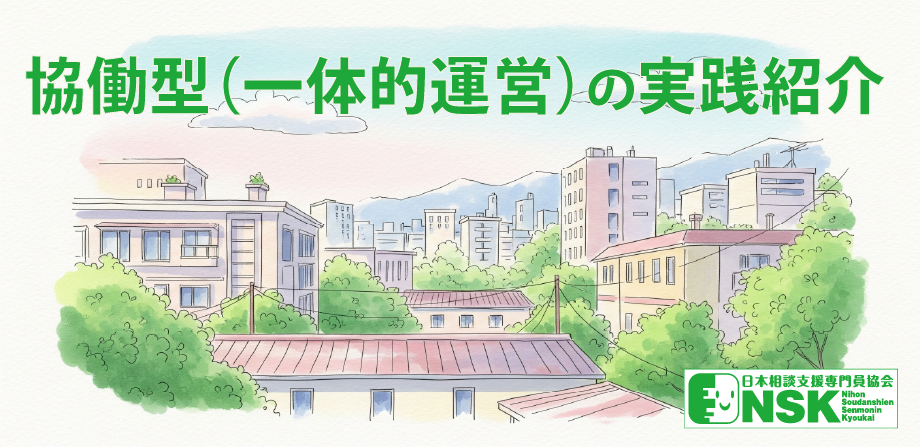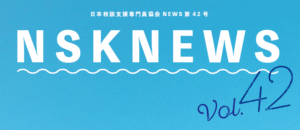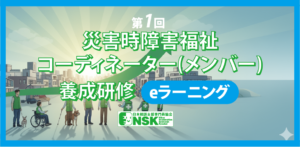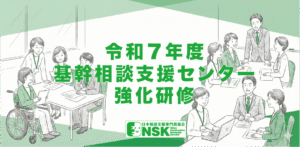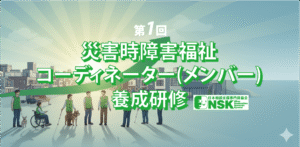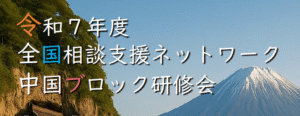目次
地域情報
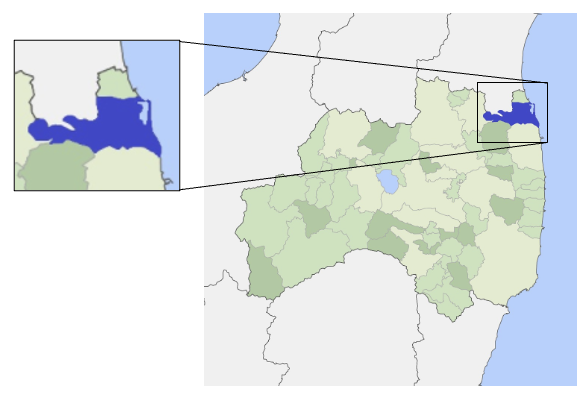
福島県 相馬市
人口
33,070人
(令和5年時点)
障害者手帳所持者数
身体
1,409人
知的
363人
精神
305人
相談支援事業所
6か所
(令和5年の5ヵ所から増加)
障がい福祉サービス事業所
- 就労継続支援B型7か所
- 生活介護4か所
- 生活訓練2か所
- 入所施設2か所
- グループホーム3か所
基幹相談支援センター
1か所
相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村からの委託により運営
支援体制
地域生活支援拠点
面的整備で設置済み
自立支援協議会
相馬市・新地町で共同設置
協働体制の経緯と構築までのプロセス
背景
- 相談支援専門員としての経験が不足 ⇒7名の相談支援専門のうち5名が令和2年度以降の配置
- 1~2名体制・兼務の事業所がほとんどで人材育成や自身の業務の検証が困難 ⇒5事業所のうち2事業所が2人態勢だが、1事業所は兼務
- 相談支援事業所単独では収入面で運営困難
相談支援事業所の基盤強化、体制整備が必要
単独事業所ではできない
経緯
- 令和6年新規相談支援事業所設置(主任相談支援門員配置)
- 相馬市・新地町相談支援事業所連絡会を基盤に機能強化型ついて検討(市町・基幹相談・相談支援アドバイザー・相談支援事業所)
- 課題を整理し、協働体制の必要性を共有し、各法人へ必要性を説明
- 令和6年10月より一体的な管理運営を開始(機能強化Ⅰ)
現在の協働体制のしくみ
構成
- 市内6事業所が連携(相馬市委託4ヵ所、新地町委託2ヵ所)
- 主任相談支援専門員を含む8名の常勤体制(主任1名、現任5名)
会議・連係体制
- 月1回対面(各1回/3ヶ月)
相馬市・新地町相談支援事業所連絡会
相馬地方相談支援事業所連絡会(南相馬市と共同)
相馬市相談支援学習会(ケース検討) - 月1回zoom(毎月第1金曜日 16:00~1時間)
相談支援ネットミーティング - 週1回zoom(毎週火曜日 9:00~30分)
情報シェアミーティング(zoom) - 24時間連絡体制(全員が携帯電話を貸与・LINEグループ)
- 基幹相談支援センター・相談支援アドバイザーとの連携
協働がうまくいった理由・継続の工夫
- 定例会議のルール化と継続的実施
-
会議の日時の固定化(例 情報シェアミーティング毎週火曜日 9:00開始)
- フラットでゆるやかな関係
-
連絡会の会長などはおかず、主任相談支援専門員が世話人としてまとめる
- zoomと対面を併用した柔軟な会議運営とAIの活用
-
zoomの利便性と活用と、会議録の作成にはAIを使用して負担を減らす
- 相談支援学習会を通じた学びの場の確保
-
定期的なケース検討の場を設け、ファシリと板書などを体験し、ケースを共有
- 協働できる心理的安全性の確保
-
同じ悩みや立場を理解しあえる仲間の存在
- 市町との課題の共有
-
会議録の共有により、リアルタイムの情報の共有と相談業務の見える化
- 基幹相談支援センター・相談支援アドバイザーとの協働体制
-
支援の交通整理や地域課題の明確化
効果・成果・課題
効果
<やってよかったなーと思うこと>
- タイムリーに相談できる人がいなかったので、ミーティングを利用して相談することができ、複数の方からアドバイスがもらえる
- 相談支援専門員同士の距離感が縮まり、士気が高まった気がする
- 事例検討も定期的に行うので、ファシリや板書のスキルを高めることができる
- 他の相談支援専門員も困難ケースを抱えていることが分かり、自分だけではなく皆頑張っているんだなと、自分のモチベーションアップにもなっている。
- 始めた当初は、こんなにもミーティングが多いと感じていて、結構時間が割かれるなと思っていましたが、メリットを多く感じていて、ミーティングが待ち遠しくなってます
成果
- 困り感と情報の共有(市町も含めて)できる
- 個別ケースから地域の課題を整理できる
- ケースを協働で担当することできる
- 相談支援事業所としての一体感が生まれる
課題
- 相談支援専門員の質と量の確保
- 委託と計画の混在の整理
- 主任相談支援専門員の不足
- 会議のマンネリ化
地域へのメッセージ・今後の展望
他地域へのメッセージ
- 孤立しない相談支援体制を、地域全体で支える仕組みへ
-
相談支援専門員の負担を軽減するとともに、地域全体として支援の質を向上させることが可能
- 協働体制はオーダーメイド
-
各事業所の強みや専門性を生かしながら、情報共有のルールや会議の運営方法、支援の役割分担を柔軟に設定することで、より効果的で実効性のある相談支援体制を構築できます。
今後の展望
- 法人の枠を超えた専門職集団へ成長する。
- サビ管や事業所の支援員へのネットワークの拡大する
- 課題を上げるだけはなく、解決策を検討する
- 次世代の人材確保と育成するリスト