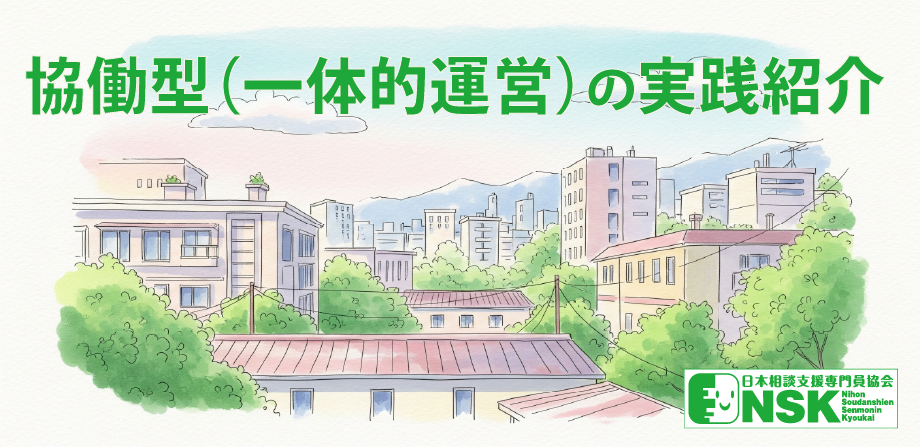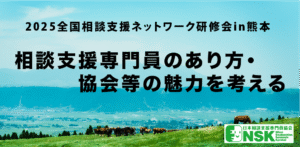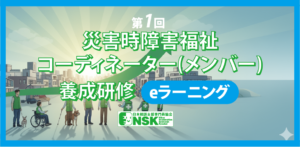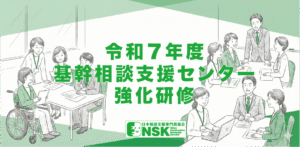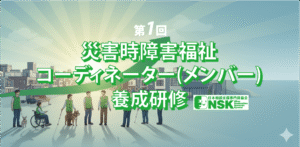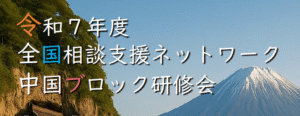長野県東御市
長野県 上小圏域
対象圏域
上田市・東御市
長和町・青木村
東御市 人口
28,831人
令和7年6月現在
基幹相談支援センター
設置済み
上小圏域基幹相談支援センター
(圏域に1ヶ所)
地域生活支援拠点
設置済み
面的整備
(圏域で整備)
指定特定相談支援事業所
圏域全体
38
事業所
うち東御市
5
事業所
圏域全体
38
事業所
うち東御市
5
事業所
機能強化型指定事業所
21/38
機能強化型事業所 (55.2%)
機能強化型事業所は
21事業所
存在します。
うち4事業体は、複数の事業所が連携する
「協働連携」の形態をとっています。
協働体制の経緯と構築までのプロセス
協働連係事業所名:相談支援センターみまき・笑明日相談室
①経緯
▪両事業所で協働連携についての話題は以前からあった新人相談員が事業収益や加算について調べた結果、基幹相談支援センター所長・主任相談員に相談
②プロセス
▪協働連携モデルや体制加算、地域生活支援拠点についての説明を受け、事業所間で検討・協議し、協働連携体制協定を締結
▪緊急時支援時のフローチャートや24時間対応当番等ルールを明確化し、事業所間で納得出来た状態で運営を開始
現在の協働体制のしくみ
| 体制 | 定例会議・研修 | 事業所間連携 |
|---|---|---|
| 笑明日相談室 相談員① 常勤専従・現任相談員② 常勤専従・初任 + 相談支援センターみまき 相談員① 常勤専従・初任 相談員② 常勤専従・初任 相談員③非常勤専従・現任 機能強化型Ⅰ型 | 頻度:毎週木曜日9:00~ 内容:運営会議、ケース検討 や地域資源の情報共有等 対面方式で毎回1時間程度の会議を実施 研修:基幹主催のGSV研修が毎月あり、会議後に各相談員が参加・事例提供をしていく | 両事業所のケース情報は共有されており、相談のしやすい体制が整備されている 支援の行き詰ったケースを連携先事業所でフォロー的に支援、又は引き継ぐ事もある それぞれの法人の別の事業でサビ管と相談員の関係も深まり、協働連携の取り組みが波及していった |
協働がうまくいった理由・継続の工夫
- 両事業所が同じ地域にあり、地域福祉の向上の為という事業所のニーズが合致した→協働連携スローガン『地域の為に』
- 笑明日相談室は経験年数の多い現任相談員がおり、初任者の多い相談みまきへケアマネジメントや地域資源について指導・OJTを行ない両事業所で支援の質向上
- 各相談員悩みを抱える事があるが、定例会議で言語化出来る安心感や、支援者としての視野や価値観の拡がりがあった
- 明らかな収益増につながり、ボランタリー的に行っていた支援にも加算が付く事でモチベーションが向上した
効果・成果・課題
- 両事業所で支援の質の向上、心理的安心感、収益向上等協働連携によるメリットを日々感じながら業務に当れている
- 令和4年に始まった協働連携体制は4年目を迎え、当初協働連携事業所は圏域で1つのみであった。令和7年では4つの事業体が出来、協働連携事業所同士の研修会や事業所見学会を開催し、圏域内での交流も盛んになっている
- 両事業所で受け持ちケース数に差があり、現任相談員の負担が高い初任者でフォローアップ出来る体制や資質の向上を図っていきたい
地域へのメッセージ・今後の展望
- 基幹から説明を受けた際に「これはメリットしかない!」と感じました。
- 詳しい方や他事業所さんに相談をするというアクションを起こせた事がこの取り組みに繋がっているのだと思います。今、業務や運営で悩んでいる事業所があれば、一歩踏み出す事で多くの事が改善に向かうと考えます。
- 事業所間連携が相談事業所のみならず、他法人・他事業所へと拡がるよう橋渡しの役割を担い、地域が繋がり合う事でより良い地域作りが出来る事に寄与していきたいです。
北海道札幌市
報告者:一般社団法人ぷらはる3 相談室ぷらうむ 細谷 恵佑
基本情報
北海道札幌市
人口
197万人
地域生活支援拠点等
面的に整備済み
市内の各エリアで
機能が整備されています
相談支援事業所
基幹相談支援センター
1ヶ所
委託相談支援事業所
18ヶ所
指定特定相談支援事業所
175ヶ所
基幹相談支援センター
1ヶ所
委託相談支援事業所
18ヶ所
指定特定相談支援事業所
175ヶ所
協議会の構成
札幌市の協議会の下に、市を構成する10区それぞれに区ごとの協議会が設置されています。
協働体制の経緯と構築までのプロセス
- 札幌市においては、人口規模や毎年増える障害福祉サービス利用者に対して、相談支援専門員の数が不足しているということで、平成27年からずっとセルフプランが許容される形での相談支援体制が続いている。
- 一人事業所で始めるにしても厳しい単価ということもあり、なかなか稼働できる相談支援事業所が増えていかない状況が続いた。立ち上がってもすぐに休止・廃止ということが続いていき思うように事業所数も伸びていかなかった。行政としても指定相談に家賃補助などの別途予算をつけるということは行っていなかった。
- セルフプランを減らしていこうという議論は協議会でも進んでいかなかった。委託相談でセルフプランを用いてのサービス調整を行っていることもあってか、計画相談率に関しては今日まで大きな課題としては取り扱われていない状況。
- そういうような状況で、複数の事業所による一体的管理運営(協働型)の制度が令和3年から始まるということになり、当事業所としても相談支援体制の拡充のためにこの制度に注目していくこととなる。
協働型スタート:令和3年12月より。PAN(ぷらうむ・あすみ・にじいろ)協働体。
白石区・豊平区・東区で活動している指定相談が協働型を組んでいる。
- せっかくできた制度なのでチャレンジしてみようということで、お付き合いのある相談支援事業所と協働型を組むことにした。
- 札幌市では地域生活支援拠点等になるためには運営規定に記載をすれば良いということだったので、自分たちで準備をすれば協働型を組めることがわかり、スタートすることができた。
- 私たちの協働型はそれぞれの事業所が異なる専門性を持っており、定期のミーティングで困りごとに対する解決策を話し合うことができるという素晴らしメリットがあることがわかった。
- にじいろは、併設する事務所で札幌市から委託を受けて緊急入所受先調整窓口事業も行っている。急に夜間・休日帯の行き先が無くなってしまった方の支援を随時調整している。札幌市に1か所しかない状況。
う ま く い っ た 理 由
- 当初はぷらうむだけが相談支援専門員を3人配置しており、他2事業所は1人体制だった。それぞれとても経験のある相談支援専門員だったが、一人事業所はどんなに経験があっても大変なことも多く、事業所の孤独感の解消やバーンアウト防止のため、週1回のズームミーティングと月1回のランミーティングを開催していた。
- 協働型の成果としては、一人事業所も機能強化Ⅰを取り続けることができたため、運営的にも増員に向けた余力を蓄えることができた。その結果として令和7年現在は他2事業所も2名体制への増員をできており、マネジメント的にも良い方向に向かっている。
現在の人員配置
ぷらうむ:相談支援専門員5人(主任2・現任2)・相談支援員1人
あすみ:相談支援専門員2人(主任1・現任1)
にじいろ:相談支援専門員2人(主任1)
その後の活動と今後の展望 KYA(協働体有志の集まり)
- 協働型を始めた後に草の根運動として、協働型が良いよということを色々な人に伝えていった。そうすると市内の協働型が増えていった。
- 札幌市では地域生活支援拠点等の整備状況は公表されておらず、PANとしてはどのように自分たちの活動を広げていくかを模索している状況だった。
- そこで、業務上面識のある他の協働型を組んでいる事業所とも連携をしていくための集まりをスタートすることとした。これを私たちはKYAと名付けている。
- KYAでは各区の状況確認を行うことや共に研修を行ったり、今後の地域生活援拠点の展望について自主的に協議している。
- 今後については、空白の区にKYAの構成員を増やしていくことを検討中。
地域へのメッセージ・今後の展望・感想
- 全国を今改めて見てみると、セルフプラン率のばらつきは大きいなと感じています。大都市に関してはセルフプランを解消しようと取り組むにしても何をどうしていいかわからないところまで、深刻な状況となっているのではないかと想像します(札幌市はそんな状況です)。
- この状況をネガティブに捉えるのではなく、セルフプランが多いということは指定相談の活躍する場がまだまだあると認識していただいて、前に進んでいくことが大切ではないだろうかと思っています。
- 指定特定が活躍して、事業所を大きくして質・量共に高めていくためには、協働型は素晴らしい制度だと思っています。全国の行政の方・基幹相談支援センターや委託相談の方たちは、指定相談がこの制度に着手しやすいような体制づくりをお願いしたいです。
- 大きな都市で活動していると、体制づくりや目の前のことを頑張っても、なんだかうまくいかないような気持になってしまうということをずっと見てきましたし体感してきました。これは色々な要因があると思いますが、改めて今大事だなと思っているのは、背伸びをせずに、個別ケースの関わりの質を高めて、事業所としての質や基準をしっかりと保ったうえで、自分たちの目の届く範囲に活動を展開していくということだろうなと考えています。行政や制度とはうまく折り合いをつけながら、自分たちの大切だと思っていることを日々発信していきたいと考えています。
- 札幌市の相談支援体制の整備状況としては、200万都市に基幹が一か所しかなかったり、セルフプランが多かったり課題が多いなと感じていますが、個々の相談支援事業所が協働型を用いてより強固な事業体になっていくことで、協議会への参画も必須になりますし、自然とよりよい地域が育まれていくのではないかと思います。実際そのような動きが見られています。